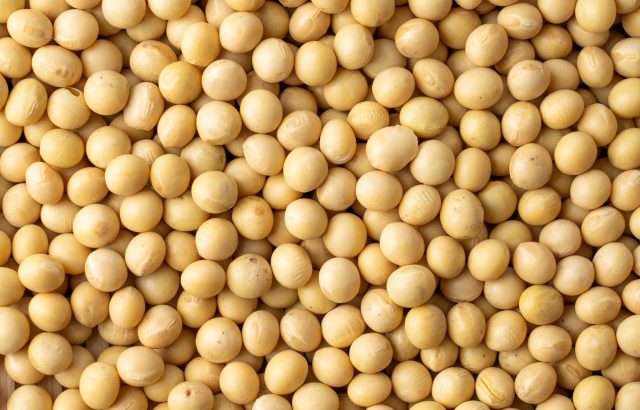食用油の価格高騰が話題になって久しいですが、その背景には世界的な需要構造の変化があります。特に大豆油・菜種油は、食用にとどまらず、燃料や産業用途へと利用が広がり、国際需給に大きな影響を与えています。
世界的な需要の変化

大豆油・菜種油の世界的な需要は急拡大を見せています。その背景には
- 人口増加と新興国の中間層拡大
- バイオディーゼル燃料への転用
があります。
まず、国連食糧農業機関(FAO)やOECDの予測によると、世界人口は2050年に約97億人に達すると見込まれています。人口増加に加え、新興国での中間層拡大が、食品加工や外食産業の拡大を通じて植物油全体の需要を押し上げています。特にインドや中国、アフリカ諸国では需要が急伸しており、インドはすでに世界第2位の植物油輸入国となっています。
食用油需要を押し上げているのは食料分野だけではありません。米国では大豆油の約3割以上がバイオ燃料に転用されており、今後さらに拡大すると予想されています。米国はガソリンやディーゼルに混合するバイオ燃料の数量義務を強化し、2026年には前年比67%増の56億ガロンを大豆油由来ディーゼル燃料に充てる方針を示しました。
供給と価格を左右する要因
まずは気候変動による影響です。たとえば世界最大の菜種輸出国であるカナダは、2021年に深刻な干ばつにより収量が激減しました。
また世界有数のヒマワリ油輸出国であるウクライナは紛争によって供給が大幅に減少しました。その結果、欧州やアジア諸国では代替として菜種油需要が急増しています。
気候リスクや需給逼迫は価格高騰を招き、日本を含む輸入国に影響を及ぼしています。
日本への影響は?

農林水産省のデータによると、日本の食用油原料の92.0%が輸入に依存している(2024年)のが現状です。
なお、大豆・菜種ともに国内自給率は極めて低く、菜種の自給率は0.1%、大豆油も国産原料比率は2%以下にとどまっています。
為替変動や国際需給の変化が価格へ直結する構造となっているため、世界的な供給不安や投機的な動きによって、国内の価格高騰や品薄リスクが高まっています。
一方で、農研機構や農水省は国産菜種の品種改良や地域振興モデルを推進しており、北海道や長野県などで国産菜種の生産拡大を模索する動きが広がっています。限界はあるものの、食料安全保障の観点から国産油糧作物への注目が高まりつつあります。
関連記事:国産大豆のニーズ高まる。国内外の大豆生産、需要と供給の現状について
人口動態やエネルギー政策、環境問題といった複合的な要因が需給を左右し、国際価格の変動が私たちの暮らしにも影響を及ぼしています。大豆油や菜種油は、もはや単なる「食用油」にとどまらないグローバル資源といえそうです。
参照サイト