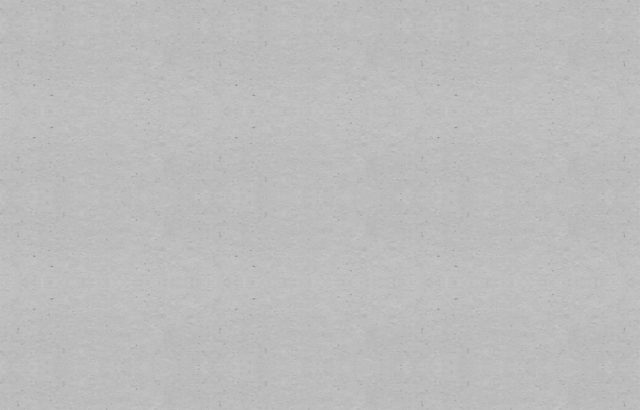紙製マルチとは、農業で利用される紙製のマルチングシートのことです。
紙マルチは古紙を原料とした生分解性の農業資材で、環境負荷の少ない持続可能な農業を実現する手段として注目されています。
紙製マルチの特徴
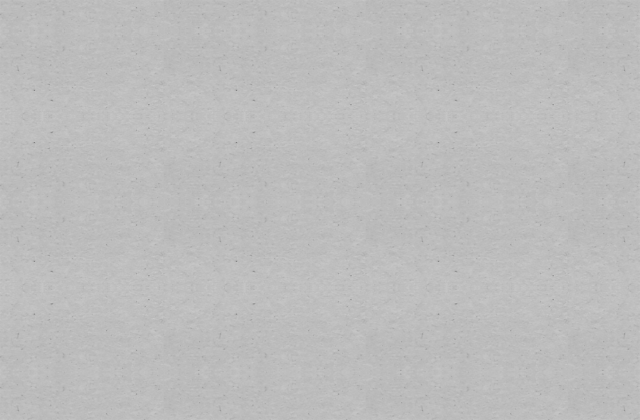
雑草抑制効果
段ボール古紙などを再利用して製造されているものは遮光性が高く、土壌表面に敷くことで雑草の発生を効果的に抑制できます。
水稲有機栽培の現場では、再生紙マルチを用いた移植栽培が行われており、50日ほどで紙が溶けるまでの間、田面の雑草はほとんど発生しません。イネ苗はその間にしっかりと生長します。その結果、後から雑草が生えてもイネ苗が競り負けることが少なくなるため、除草作業の負担が減るメリットもあります。
地温上昇の抑制
ポリエチレン製の黒マルチの場合、太陽光を吸収して地温を上昇させる性質があるのに対し、紙マルチはその遮光性と通気性により真夏の地表温度を5~10℃抑えることが実証されています。この性質は、近年深刻化している夏季の高温障害の抑制にも有効です。
王子エフテックス株式会社が販売する紙製マルチ「OJIサステナマルチ」を用いた試験では、中温性や冷涼性の野菜栽培において生育不良が改善され、最大で10%程度の収量向上が確認されています。
高温条件下でも安定した生育環境を確保できる点は、気候変動への適応策としても期待されます。
廃棄作業の省力化
ポリマルチでは収穫後にマルチを一枚ずつ手作業で剥がす必要がありますが、紙マルチではその手間が省けます。紙製マルチは、土壌中の微生物によって分解され、最終的には自然に還るよう設計されており、マルチの回収・洗浄・焼却といった煩雑な作業が不要に。これにより、作業負担を大幅に軽減することができます。
この特徴は、特に農業現場の人手不足や高齢化が進む中で重要視されています。
有機農業や環境配慮型農業との親和性
化学合成資材の使用が制限される中で、土に負担をかけない紙製マルチは、有機農業において除草剤を使わない栽培技術の一つとして注目されています。地域の環境保全や脱炭素への意識が高まる中、紙製マルチの活用は農業現場でのSDGs実践の一環としても評価されています。
従来のマルチとの違い
前述したように、一般的に使用されているポリエチレン(PE)製マルチや生分解性マルチと比べ、紙製マルチには地温の上昇を大きく抑えるという特長があります。
また温度の変動幅が小さいことも特徴としてあげられます。これは紙製マルチの断熱性と透湿性のバランスに加え、紙表面からの蒸発によって地温上昇が抑制される潜熱効果によるものと考えられています。
よって紙製マルチの使用は、特に夏季の高温期において、キャベツやハクサイ、シュンギク、ダイコン、ホウレンソウなどの栽培に適しています。実際に、夏まきのチンゲンサイ栽培や秋どりレタス、ホウレンソウ、ミズナの栽培でも紙製マルチの使用によって地温が抑えられ、生育や収量が良好だったとする研究報告もあります。特に高温期には、地温の上昇を抑えることが欠株の防止や地下部の健全な発育に寄与し、結果的に地上部の生育にも良い影響を与えるとされています。
加えて、紙製マルチは使い終わった後に剥がす作業が不要で、そのまま土壌に鋤き込むことができます。ポリマルチに比べて初期導入コストはやや高めですが、保管性が高く余剰分も翌シーズンに無駄なく使え、人件費や廃棄コストの削減にもつながることから、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れた資材といえます。
紙製マルチ使用時の留意点

紙製マルチは多くの利点がありますが、使用時にはいくつか注意が必要です。
まず、素材が紙のため、水濡れによる劣化を防ぐ必要があります。そのため、保管時には湿気や雨に十分注意し、展張作業は風の弱い日に行うことが求められます。展張する際は、PEマルチよりもやや緩めに張ることが推奨されています。展張後は畝まわりをしっかりと覆土し、風によるめくれや飛散を防ぎます。
また、紙製マルチは使用後にそのまま土に鋤き込むことができますが、紙が乾燥して飛散しないよう、周囲に配慮した作業を行うことが望まれます。
なお、紙製マルチの耐候性は約60日間を目安に設計されており、これは天候や土壌中の微生物の活性度によって変動します。そのため、使用にあたっては作物の在圃期間との調整が必要になります。
紙製マルチの特性を十分理解し、作物や気象条件に応じた適切な運用を行ってください。
参考文献:AGRI JOURNAL編集部『AGRI JOURNAL vol.35』(アクセスインターナショナル、2025年)
参照サイト