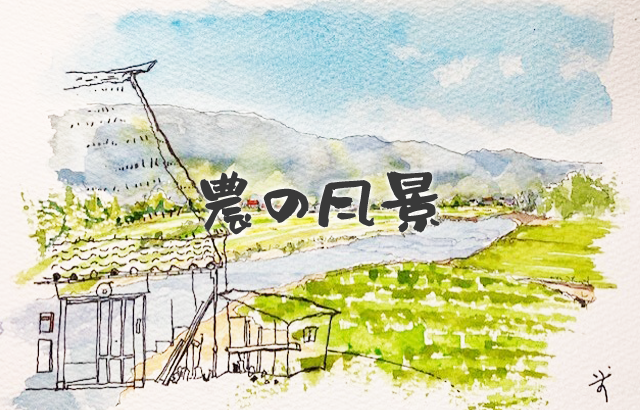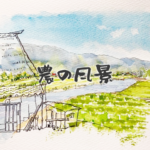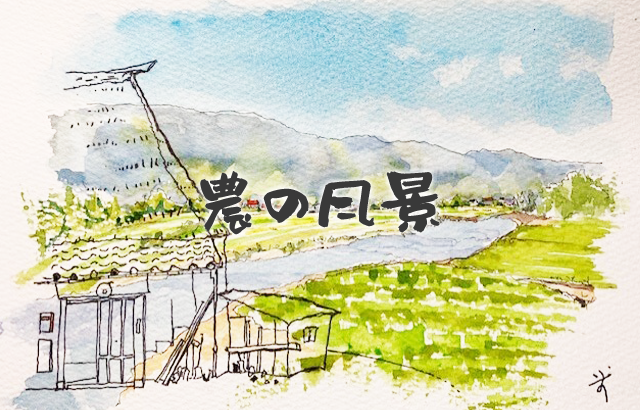2025年9月23日から2週間かけベルリン在住の友人の女流画家を訪ねた。今回から、何回かに分けてドイツ紀行を報告する。


ベルリン近郊にあるポツダム市のサンスーシ宮殿を訪れた。サンスーシ宮殿は、学問・芸術等の文化に関心が深かったフリードリヒ2世(大王)が建てた宮殿である。フリードリヒ2世は、軍隊を整備しプロイセン王国の領土を拡大した父親からの反対にもめげずに、自ら、芸術、音楽、絵画に精通し、多くの芸術家を育てた。また、自らもフルート奏者として有名だった。2世はヴォルテールやオイラーをはじめ著名な学者たちをベルリンに集め、少数の親しい友人たちと音楽や芸術についての議論を楽しんでいたことでも知られている。
フリードリヒ2世がサンスーシに滞在していた頃の日本は徳川吉宗が大御所になり9代将軍家重の時代であったが、歴代将軍が文化や芸術について素養があったとは必ずしも言えない。武家を中心とした時代の日本では、絵画や芸術や文化は他人に自分の力を誇示するための1つの道具にすぎなかったと考えられる。例えば、秀吉と千利休の関係をみればわかるであろう。また、松尾芭蕉や葛飾北斎などを支援したのは、当時の権力者の徳川家や大名ではなく、市政の商人たちだったことからも明らかだろう。
この背景には、大名が芸術家を抱えても、徳川幕府が認めなければ、幕府から叱責を受け、お家が危うくなることを恐れたことによる。例えば、前述した北斎は、幕府による天保の改革によって江戸では絵の制作が制限され、信州小布施の豪農・豪商の高井鴻山に招かれ、新たな境地にチャレンジし、88歳で岩松院本堂大間の天井絵「鳳凰図」を手がけたことを考えればうなずけるだろう。
この幕藩体制の中に、日本における芸術・文化の位置づけ、すなわち、「お上(国)が認めた絵画や音楽などが“芸術”なのだ」との文化構造を見ることができる。かつて、小沢征爾は東京芸大出身者でないために、NHK交響楽団を指揮できず大問題になったことがあった。また、イギリス在住(イギリス国籍)のピアニスト内田光子の場合にも当てはまる。彼女はウィーン音楽院で音楽を学び、1975年のショパン・コンクールで2位に入賞したが、日本国内での評価は低くロンドンに拠点を移して活躍している。
これらの音楽家に対する姿勢は、日本国民の芸術に対する考え方にも繋がっている。つまり、日本では、前述したように、国が認めた音楽や絵画を”芸術“だとみなし、国がお墨付きを与えない音楽や絵画を低く評価してしまう文化構造が存在しているのである。


これに対し、ドイツの芸術に対する文化構造は大きく異なっており、アーティストへの支援が手厚く「文化は生きるために不可欠」との考えがある。例えば、コロナ下には芸術家のために60万円を支援したり、ベルリンには、公立ギャラリーでの展覧会参加アーティストへ時給70ユーロの報酬を支払う制度がある。さらに、ドイツでは芸術活動を目的とした長期滞在を可能にするアーティストビザがあり、画家や音楽家はこのビザを取得している。これは、国が音楽家や画家を職業として認めていることを意味している。加えて、このビザを取得するとKSK(Künstlersozialkasse)と言う芸術家社会保障制度に加入することができる。この制度は、多くの芸術家はフリーランスとして働いているので、一般的な社会人が加入している公的保険に入れるチャンスがない。KSKはその点を考慮した芸術家向けの保険制度なのだ。
また、ベルリンでは毎年8月に、「ランゲ ナハト デアミュージアム(Lange Nacht der Museen:長い夜の美術館の日)」というイベントがある。このイベントは、夜中の2時までベルリン市内の美術館が無料で開放され、地下鉄を含む市内のすべての交通機関が動き、市民が真夏の夢を見られるかのように美術館の絵画を鑑賞することができるのだ。このイベントには多くの市民が参加し、各自が、お気に入りの美術館に行き、お気に入りの絵画の前で、納得いくまで絵を鑑賞することができる。
このドイツ市民の姿には、日本のような「お上が認めたものが芸術なのだ」との妙な意識はなく、自分が気に入った絵画や音楽が芸術だとの“個の意識”が表れている。その意識は「何が好きなのか、何が良いのかは他人ではなく自分が決める」とのドイツ人の自由に対する考えから生まれているのだ。そして、その背景には、第2次世界大戦中のナチスの政策に加担していたドイツ市民の過去への反省があると言われている。
稲田宗一郎(いなだ そういちろう)