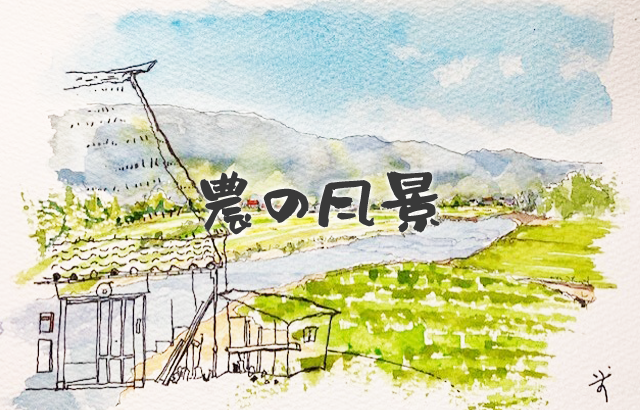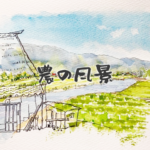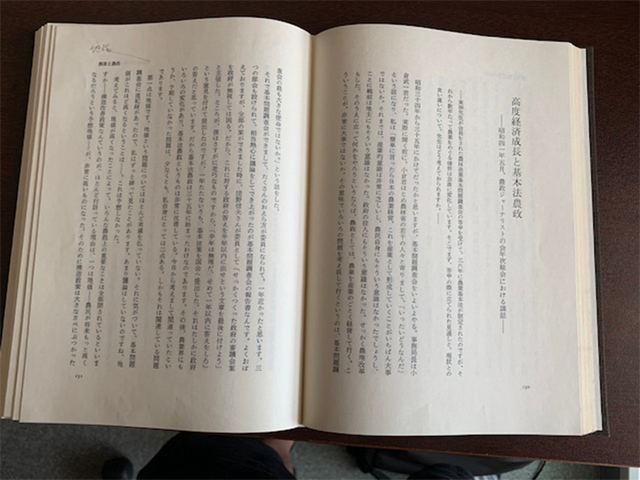
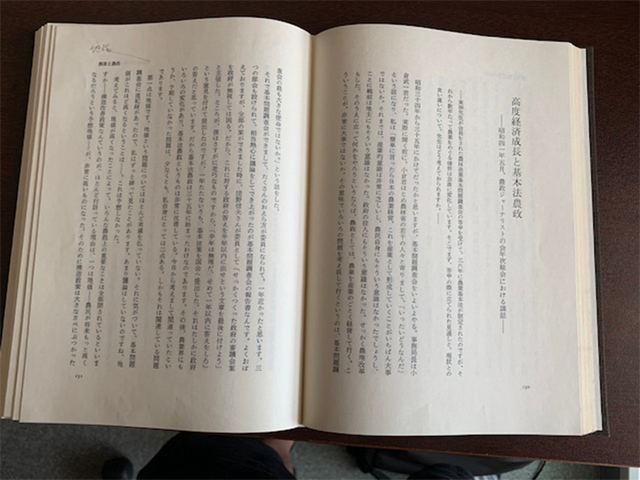
農林漁業基本問題調査会における東畑精一の誤算
日本の農業政策には1つの背景がある。その背景を一言で言えば「構造改革=規模拡大」である。今回は、この「構造改革=規模拡大」はどのような背景から出てきたのかについて考察する。この考察は、昭和36年の農業基本法の成立に関係しているので、この農業基本法に関係した一人の学者の話を紹介する。
政府は、日本が高度経済成長に向かっていた昭和35年に『農林漁業基本問題調査会』を組織した。事務局長は後の農林事務次官の小倉武一であり、調査会の座長には東京大学の東畑精一がついた。
東畑は昭和41年5月の『農政ジャーナリストの会年次総会』の講演で、農政ジャーナリストの会会長の団野信夫の「『農林漁業基本問題調査会』の答申の際に建てられた見通しと現状との食い違いについてどのように考えているのか」の質問に対し、次のように答えている。
東畑は、「当時予期していなかった問題は2つあった、1つは地価の問題であり、地価が高くなって、農業構造改善政策がほとんど行き詰まってしまったこと、2つは、構造政策と生産性の向上が続けば、農民がどんどん出ていく、農民が土地をすてて出ていくことになれば、その土地を他人に委託したり、売却したりして、農村に残った人間にとっては農業生産規模を大きくしうる可能性が非常に高まり、その結果、農業の生産性も高まり、農工間の所得格差も縮小すると考えていたが、この考えが間違っていた」と答え、「1つ目の地価の高騰は、農民が将来の価格高騰を予測して農地を手放さず構造改革が進まなかった事、2つ目は、農民は稼ぎに農外に出るけれども細君と両親が農業をする、いわゆる、3ちゃん農業が主流になり、農地は余らず規模拡大が進まなかった」と回想している。
現代も続く2つの問題
この談話の1つ目の地価高騰は現在でも形を変えて続いている。農村地域では地価高騰ではなく農地価格が下落している。しかも、こららの地域では、新たに農地を買う農家はなく、また、地代なしでも借り手がいない状況となっている。親から農地を相続し、自作地に加え、近隣の農地を借りてコメを作っていた農家も高齢化したために、借りていた農地を返却する事例が全国で増えている。2つ目の3ちゃん農業も、定年後地元に戻った農民が農業を続けていたが、その定年帰農農家も高齢化し農業生産から撤退している。まさに、地域農業消滅の姿が垣間見えるのである。
かつて、友人の農家は、「大規模化された農業法人は利益が出なければ撤退する。しかし、撤退した後の農地はどうなるのか、誰が農地を管理するのか。おそらく耕作放棄地になる。なぜならば、大規模農業法人の出現により、その地域のもとからいた農家は、既に、農業を止めて耕作していないからだ」と語っていたが、現在の状況は、大規模農業法人だけではなく、地域の家族農業経営さえも高齢化により農業生産から撤退する状況となり、全国で耕作放棄地が増加してきているのである。
今から65年以上も前に「農林漁業基本問題調査会」で議論されてきた時代には、日本の農家は調査会が望んだ規模拡大を実現した自立経営農家の形ではなく兼業農家の形で存続してきたが、65年後の現在は、日本の農家は、もはや、兼業農家の形態でさえ残らなくなってきたのである。
《なぜ、このような事態が生まれてしまったのか?》
東畑精一の品格
東畑はこの農林漁業基本問題調査会の経験から、その後、「農業の事を論じる」ことを意識的にさけてきたと語っている。ある時、滋賀県の夏期大学で講演した時に、農協出身の前知事が、2日に渡って最前列で一生懸命講演を聞いていたが、その後の懇親会で、前知事は「農政の権威であるあなたが、農業の話を一言もしないとはけしからん」と言ったそうだ。東畑は「権威はとうに自ら失くした。『農林漁業基本問題調査会』で自分は大きな間違いをした、だから、私は農業の事を言わなかったのです」と正直に答えたと回想している。
なぜ、この話を紹介したのかと言えば、自分の間違いを素直に認め「農業の事を語るのをやめた」と言う東畑の姿勢の中に、筆者は、1人の学者、いや、1人の人間としての品格を感じたからだ。
この東畑の姿勢に対し、昭和36年の農業基本法以降、一貫して、規模拡大を政策の柱として農業政策を展開してきた政治家や官僚や学者たちは、現在の日本農業、すなわち、「2020年の全農業経営体数に占める法人経営の割合は2.9%、10ヘクタール以上の割合は5.4%と極めて少なく、3ヘクタール未満の経営体数の割合は84.0%になっている(農水省の農業センサス)」現状をどのように感じているのだろうか。
少なくとも、
《自分の誤りを認め、「農業の事を論じる」ことを避けてきた東畑とは明らかに異なっている》
と筆者には思えるのだ。
現在の政治家・官僚・学者たちの多くは、65年以上続けてきた「構造改革=規模拡大」政策の誤りを認めてはいない。しかし、現場の農村地域では、農家は規模拡大どころか農業から撤退しているのだ。その結果、コメが不足し、コメ価格が高騰しているのだ。
にもかかわらず、間違った自分を恥じて、規模拡大を語らなくなった政治家や役人や学者がいないという事実に、今の日本の、いや、日本人の危うさを感じてしまうのだ。
稲田宗一郎(いなだ そういちろう)