気候変動や人口増加に直面する中、農業は持続可能であることが求められます。そこで注目を集めるのが遺伝子組換え技術です。遺伝子組み換え技術は、病害虫に強い作物や栄養価の高い作物の開発、気候変動に対応できる新品種の育成などにつながる技術といえます。
あらためて遺伝子組換えとは何か
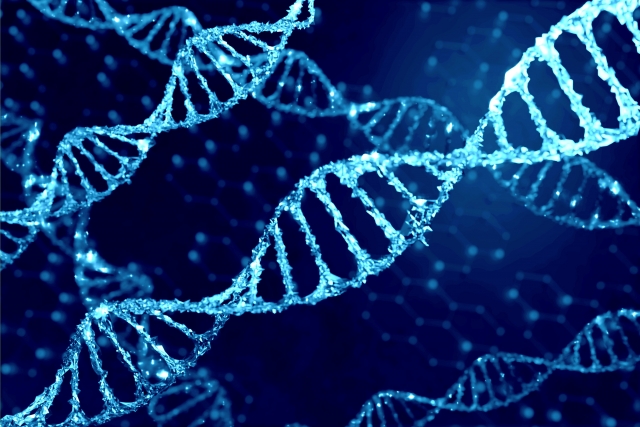
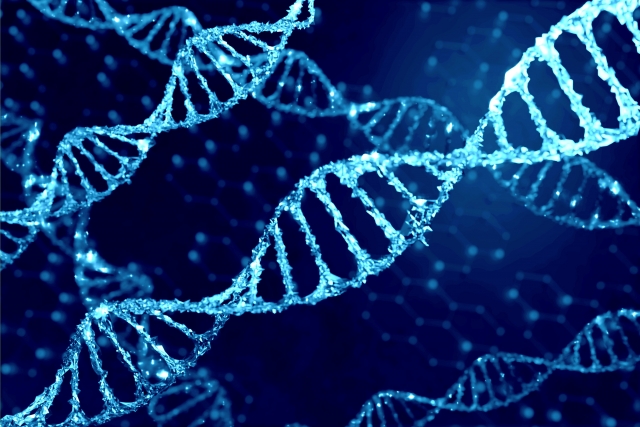
遺伝子組換えとは、外来遺伝子を導入して作物の性質を変える技術を指します。1990年代後半に商業化が進み、代表的な例として害虫に強い性質を持つ「Btトウモロコシ」や除草剤耐性大豆が登場。これにより、農薬使用量の削減や収量の安定化が実現しました。
ゲノム編集との違い
一方でゲノム編集(例:CRISPR-Cas9)は、外部の遺伝子を導入せず、既存の遺伝子を改変する技術です。法制度上、遺伝子組換えとゲノム編集では扱いが異なります。
関連記事:『ゲノム編集』農作物に注目が高まる?!ゲノム編集とは
遺伝子組み換え技術等の研究事例


宇都宮大学や鳥取大学、農研機構等の共同研究チームは、乾燥ストレスに強いコムギを開発しました。このコムギは気候変動がもたらす異常気象への適応策として期待されています。研究では耐乾性に関与する植物ホルモン「アブシジン酸」の応答制御を強化することで、乾燥環境下での生育を可能にしました。
かねてより注目を集めていた遺伝子組み換え作物には、冒頭でも述べたような害虫抵抗性を持つものや、栄養を強化した作物があげられます。
たとえば、近年の研究(2024年)には、βカロテンを多く含む「ゴールデンレタス」の開発や、ゲノム編集によってグルテンを改変した低アレルゲンコムギの開発などがあります。
なお、世界で初めて商用栽培された遺伝子組み換え作物であるフレーバーセーバートマトは、作物の熟期に関わる遺伝子の働きを調節したもので、流通過程でトマトが腐敗してしまうのを防止できるようになっただけでなく、トマトの風味の改善にもつながりました。
また千葉大学柏の葉キャンパス内に新設された研究拠点では、遺伝子組み換えされた稲を用いた「飲むワクチン米」の開発が進められています。これにより、注射が苦手な子どもや高齢者、注射器が不足する発展途上国での活用が期待されています。
遺伝子組み換え等の技術は、食料問題や栄養不足への解決策として注目されており、農業の領域だけでなく、人の健康を支える技術へと広がりを見せています。
遺伝子組み換え技術の課題と展望


社会的理解とのギャップ
さまざまな課題の解決につながると期待される遺伝子組み換え技術ですが、「遺伝子組換え=危険」という誤解がまだ残っています。科学的には安全性評価が行われているものの、社会的理解との間にはギャップがあるといえます。
なお、農林水産省および消費者庁は、GM食品(GM:Genetically modified、遺伝子組み換え)の表示義務制度を設けていますが、ゲノム編集食品については2025年8月現在、表示義務がありません。このこともまた、消費者の混乱を招く可能性があります。
持続可能性につながる役割
まだまだ社会的理解との間にギャップがある遺伝子組み換え技術ですが、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の17の目標のうち、「2.飢餓をゼロに」「13.気候変動に具体的な対策を」等に貢献する可能性を持っています。
たとえば、気候変動により干ばつや高温、塩害といった環境ストレスが増大しています。そこで遺伝子組換え技術等による耐性作物の開発に期待が高まります。また、病害虫の発生域拡大といった課題にも対応できれば、農薬使用量の削減や病害虫の被害低減につながります。このことは作物の安定生産・供給にも寄与するといえます。
また、遺伝子組み換え技術にAI・ドローンを活用した病害虫防除策などが組み合わさることで、より効率的で持続可能な農業システムが実現することが期待できます。
遺伝子組換え技術は、誤解されている部分もあることから、いまだに「賛否両論を巻き起こす存在」と捉えられるかもしれません。しかし、いまや世界的な食料・環境問題の解決策として再評価されています。国内外で、大学や研究機関による新たな品種開発が進み、農業の持続可能性や付加価値創出に向けた応用が進んでいます。
参照サイト
- 干ばつに強く、水を節約して育つコムギの開発に成功|宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター
- 乾燥ストレスに強いパンコムギで、干ばつや気候変動に立ち向かう 山口大学 妻鹿准教授にインタビュー|TERRARIUM | テラリウム
- コメで作った飲むワクチン「ムコライス」の実現に向けて大きな一歩-ヒトでの安全性と免疫原性が確認されました- | 国立大学法人 千葉大学|Chiba University
- 世界規模の”口から摂取する”新しい形のワクチンへ コメ型経口ワクチン「MucoRice」の再委託研究を受託 | 朝日工業社のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー
- 東大と千葉大、コメで作った飲むワクチン「ムコライス」のヒトでの安全性と免疫原性を確認 – 日本経済新聞
- 遺伝子組換え技術により、食品の風味の改善や
- 遺伝子組み換え技術の最新動向サマリー( 2024年9月) – 日本バイオ作物ネットワーク
- Boosting pro‐vitamin A content and bioaccessibility in leaves by combining engineered biosynthesis and storage pathways with high‐light treatments – Morelli – 2024 – The Plant Journal – Wiley Online Library
- ゲノム編集によりグルテンを改変した低アレルゲン小麦の作出
- グルテンなしの小麦? | Nature ダイジェスト
































